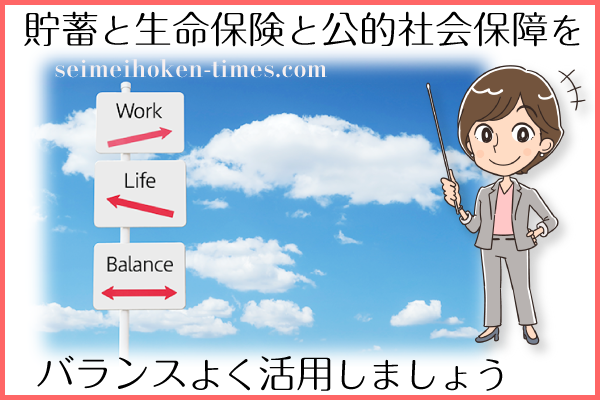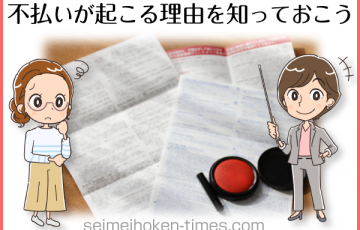お金のことは、学校では教えてくれない
あなたや家族に、想定外の「もしも」の出来事があったとき、あなたの生活はどのように変化するでしょうか?
それを突き詰め、自力での備えだけでは不足する部分を補うためのものが、生命保険です。
しかし、どのようなできごとに対し、どのような備えをしたらよいのでしょうか?
とても大切なことなのに、学校では教えてくれません。
社会人になって自分の保険証を持つようになり、結婚して子供を産み、ローンを組んでマイホームを購入して・・・こういったライフイベントを経験するごとに、少しずつ覚えていくのが日本です。
でも、これでは何かが起こってからの対応になってしまいます。
いざというときに困らない、なんとか生活していけるだけの備えをしておくためには、覚えておくべき・知っておくべきことがたくさんあります。
お金に関する知識をマネーリテラシーやファンナンシャルリテラシーといい、最近はビジネス書やビジネス雑誌でもよく見かけるようになりました。
それだけ、意識する人が増えたということなのでしょう。
これを知っているかどうかで、お金持ちはより一層お金持ちになるし、お金のない人は悪循環の中でもがくことになります。
マネーリテラシー?
ファイナンシャルリテラシー??
一体どういうものなのでしょうか。
日本で340万部、世界で3000万部売れたという、ロバート キヨサキさんの『金持ち父さん貧乏父さん』は非常にわかりやすく、日本では習わないファイナンシャルリテラシーについて説明してくれています。
そして、収入の方法が違えばお金に対する考え方や、お金の流れが変わることをわかりやすく説明したのが、同じ金持ち父さんシリーズの金持ち父さんの『キャッシュフロー・クワドラント』です。
私がこの本を読んだのは20代の頃でしたが、頭がショートしましたね。
これらを読んで、給与収入しか収入源のない私に何かあったら、どういう生活になってしまうのだろう・・・と真剣に考えさせられました。
そう、生命保険というのはもしものときの生活を守るものですが、自分の置かれている状況がわかってこそ、必要な保障額もわかるのです。
段階によって備えは変わる!? 緊急事態の種類とリスクを考えよう
あなたが奥さんと2人の子供を抱える、一家の大黒柱だとしましょう。
もしあなたの身に何か緊急事態が起こったとしたら、どうなるでしょうか?
まず、その緊急事態にはどのようなレベルが存在するか考えなくてはなりません。
私達にこの先起こりうる危機は、数えきれないくらいたくさんあります。
想像もつきません。
ですから、想像できるものをパターン別に考えていきましょう。
下の図を見てください。
<人生の危機にもいろいろある の図>
私達が考える「もしも」は、大きく分けてケガか病気です。
そして、一定期間の療養で元通りに復帰できるのか、それとも一生障害を背負うことになるのか・・・誰にもわかりません。
では、私達はこれらの危機に対し、どのようにしたらよいのでしょうか?
まず、それぞれの場合に必要な費用と期間を考えましょう。
例えば、死亡してしまった場合は、葬儀費用などを出したあと、子供達が社会人になるまで教育費が続きますし、妻の生活費は妻が亡くなるまで続きます。
命はとりとめても、大きな怪我や大病をしてしまって社会復帰できない場合も、同じように教育費と生活費が必要です。
死亡した時との違いは、あなた自身の生活費や医療費がかかること、場合によっては介護費用がかかるかもしれないこと。
また、仮に一時戦線離脱しても、なんとか社会復帰を果たしたとしましょう。
しかし、その場合にはなかなか元の通りの働き方ができず、制約を受けてしまうことが多くなります。
必然的に、収入(給与)は以前より下がります。
その下がった収入分の費用が必要となります。
病気にせよケガにせよ、もしものときにどれくらいのダメージを受けるか、全くの元通りにいくかどうか・・・それは誰にもわかりません。
もしもの時には、何に頼る?
ここからは、生命保険にからめて考えていきたいと思います。
上に挙げた人生の危機的状況に陥ったとき、あなたはどうしますか?
<家庭が大ピンチ‼ どうやって対処する?>
【1】自分の貯蓄で乗り切るさ。
【2】生命保険で備えてあるから、大丈夫。
【3】公的社会保障があるから、なんとかなると思う。
【4】考えていない(考えたくない)
【5】国がなんとかしてくれるんじゃない?
【1】でいける人、相当貯めているハズですね?(それとも、不労所得がある?)
【2】生命保険の保障内容と不払い条項を、もう一度確認しましょう。
【3】公的保障の種類と金額を、勉強しましょう。
そして、【4】と【5】・・・実に多いのが、この軍団ではないでしょうか。
現実問題としてとらえていないというか、思考が停止してしまっていますね。
本当に、何の備えもなくなんとかなるものでしょうか?
確かに、小さなケガなら大丈夫でも、大きな障害が残った場合には一生分のお金が必要になります。
それに、「もしも」の事態もなんとかすり抜けて、病気も事故も経験しないという人もいますから、起こるかわからないことを過度に心配するのは考えものですよね。
では、私はどういうつもりでいるか?
全部です(*´ω`)
まず、数週間程度の戦線離脱なら、【1】の貯蓄で乗り切ります。
そして、もらえるものがあるのなら、同時に【3】の保障を請求します。
それでも厳しかったら、私は医療保険に加入していないので、【2】として今加入している生命保険を1つずつ解約していきます。(そのために、複数に分けて加入しています。)
それでも無理・・・という事態は?
【4】、考えません。(∩´∀`)∩
もともと持病のある私は、今できるだけの備えと、将来に向けての積立を行っています。
今の生活に支障のない範囲で。
生活もかなり小さくしていますから、今の時点でできる自助努力はしているのです。
ですから、これ以上は起こるかわからないできごとを考えるのは辞めました。
それでもなんとかならないのなら、もう全てをなげうって【5】の生活保護・・・ですかね。
でも、公的なお金で生活するということは、他の人達に生かされているということです。
ですから、基本的にはこの選択肢はなしです。
やはり、自分の力で子供を育て、生活していきたいですからね。
この方法は、本当に生きるか死ぬかの最後の場面に選択する方法でしょう。
そんなわけで、私がもしもの事態に陥ったら、そのケガや病気の程度によって対応を変えます。
全てを生命保険に頼るとか、貯蓄で乗り切ろうとは思っていません。
私の選択肢が【1】~【5】の全て、となったのは状況に応じて対応を変える、そしてもしものことをくよくよ考えすぎないようにする、という意味なのです。
公的社会保障に何があるか、知っていますか?
日本人、特に女性にありがちなのが、過度な不安に対する過剰な生命保険。
夫にもしものことがあったら子供と自分の生活はどうなるのか、子供に十分な教育を受けさせてあげられるか、心配になるからです。
これは、母の愛情ゆえのことで、男性よりも過度に心配してしまうのは、母性によるところがあるのではないかな、と思います。
しかし、既にお伝えした通り、全て預貯金で乗り切ろうとしなくてもいいし、病気やケガの程度によっては家族一生分の生活を今の貯蓄で乗り切るのは難しいですよね。
だからこそ、生命保険に頼りたくなるのはよくわかります。
しかし、生命保険が万能かといえば、そうではないのです。
どうしても生命保険では対応できないこと、支払い対象とならないことがあるのです。
これについては<よくある生命保険のムダ03「保険金不払い条項が多すぎる」><よくある生命保険のムダ04「高すぎる医療保険」>で詳しくお伝えしていますが、いくら毎月高額な保険料を収めていようが、保険会社が払ってくれなければ、なんの生活の足しにもならないのです。
日本はありがたいことに、国民皆保険制度によって、医療費は私達現役世代なら基本3割、高齢者なら1割の自己負担で医療を受けられることになっています。
もしもの事態に私達を救ってくれる制度は、他にもあります。
厚労省が日本における社会保障の仕組みを「ゆりかごから墓場まで」と題したコラムで、図式化しています。
国が支えてくれる制度の一覧は、こちらを見るとわかりやすいでしょう。
大きく下の4つの分野に分けて、色別で示してあります。
【1】保健・医療
【2】社会福祉等
【3】所得保障
【4】雇用
これらは切っても切れない関係で、【1】で病気やケガによる障害を受けたら、【2】の社会福祉、それから【3】所得の保障を受ける必要があります。
障害を抱えながら働くことを考えると、【4】の雇用も関係してきます。
そして、病気による障害を防ぐためにも、また【1】の保健分野が必要となってくるのです。
国民生活を生涯にわたって支える、具体的な社会保障制度にはどのようなものがあるのでしょうか?
<病気やケガで働けなくなったときの制度>
- 高額療養費制度 (全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき)
- 傷病手当金 (全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき)
- 療養費 (全国健康保険協会 医療費の全額を負担したとき)
<一家の大黒柱が障害を負った・亡くなった場合の制度>
- 障害年金 (日本年金機構 障害年金)
- 遺族年金 (日本年金機構 遺族年金)
- 生活保護 (厚生労働省 生活保護制度)
これらは現金で支給される制度です。(生命保険は現物支給もあり)
サービス(医療や介護)という現物支給を含めると、多岐にわたります。
いかがでしょうか?
私達は日本に住んで、しっかりと納めるべきものを納めていれば、これらの制度に守られているのです。
もしもの緊急事態に、全て自分達の預貯金でなんとかしようと思わなくてもいいんです。
ということは、起こるかわからない事態を過剰に心配し、今の生活に支障が出るくらい過剰な生命保険に加入する必要はないのです。
確かに、国に任せておけばいいかと言えば、そうでもありません。
高額療養費制度についても、必ずしもその限度額を超えたら対象となるわけではありません。
実際、私も請求してみて「不支給通知書」を受け取るなんて、思いもしませんでした。
(高額療養費の不支給については、<「病気があると、生命保険の加入は不利!!」~実際の生保事例09~>の記事でお伝えしています)
自助努力を怠ってはいけないし、かといって、過度に先回りして備えるのも、「今」を生きていないことになります。
貯蓄・生命保険・公的社会保障をバランスよく組み込んで、それ以上の想定外の緊急事態については「天にまかせる」くらいの気持ちでもいいと思いませんか?(*^-^*)