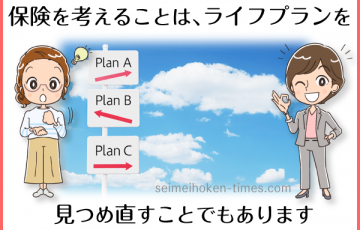生命保険は、社会人の常識ですか!?
生命保険って、社会人になれば入るのが当然と思っている方が多いと思います。
当たりまえの固定費という感じでね。
でも、ちょっと待って。
生命保険って、本当に全ての人に必要なものなのでしょうか?
生命保険が必要な時って、どういう時でしょう?
どういう時に生命保険に頼るかいう考え方の方が、イメージがつきやすいかもしませんね。
一言で言ってしまえば、「もしもの時」です。
では、「もしも」って、どういう時・状況を指すのでしょう。
<人生における“もしも”は、どんな時?>
- 病気や怪我で入院した
- 病気や怪我で入院はしないけれども、働けない
- 働けないというほどではないが、病気や怪我で収入が減ってしまった
- 大黒柱(夫、父親)が死亡した
- 大黒柱(夫、父親)が障害者になってしまった
- (自営の場合)会社が倒産した
- (サラリーマンの場合)リストラされた
- 家族(親)に介護が必要になった
こんなところでしょうか。
近年、高齢社会を迎えて、介護に関する生活不安も増えてきたと思います。
生活習慣病の増加で働けない・障害を負ってしまったという人は、実は高齢者だけではなくて働き盛りの世代にも増加しました。
つまり、子供を抱えた一家の大黒柱であるお父さんが、要介護の状態になってしまうこともあるのです。
<“もしも”の時に、困ることって?>
- 生活費
- 教育費
- 住宅費
- 介護費
- 介護のための時間、労力
(介護に関しては、介護する側もされる側もあります)
上4つはお金に関することです。
介護に関して病院でよく言われることは、「お金を出すか、手を出すか」です。
しかし、いくらお金を出しても入居待ちで施設に入れないということもあるので、お金だけではなくて、実際は介護にあたる時間と労力の問題も出てきます。
(結局は働けないので、上4つのお金の問題につながるのですけれど。)
私はシングルマザーなので、私の稼ぎが子供の将来に影響します。
私に上で挙げたような「もしも」の自体が起こった時、同様に上で挙げた5つの困ることが我が家に起こります。
今は私と子供を支えてくれている母親も、いずれは私が支える日も来るでしょう。
大黒柱である私自身が元気でも、母親に介護が必要な状態になったら、やはり「もしも」の状態になってしまうのです。
こういった不安を解消すべく世に出て来たのが、生命保険です。
そして、生命保険の加入について考える時には、
- 生活費
- 教育費
- 住宅費
- 介護費
- 介護のための時間、労力
の5つについて自分はどう考えるのか、自身の人生観が必要になってくるのです。
逆に言ってしまえば、自身の人生観やライフプランなくして、生命保険を語ることはできないのです。
結論を申しますと、人それぞれ違う人生ですから、一律「社会人になったら保険に入る」というのは間違い、ということになりますね。
生命保険は、本当に必要なのか?
こちら(「初めての妊娠・出産と保険」~実際の生命保険関連の事例01~)でもお伝えした通り、私が生命保険に入ったのは、実はよくあるパターンで、
「社会人になったから、保険の1つも入っておかないと」
というものに、営業の若者を助けてあげようという母親の親心からでした。
ファイナンシャルリテラシーのかけらもありませんでしたね(;´∀`)
そして、わけもわからず入った保険の恩恵にあずかったのは、妊娠中の切迫早産の入院、緊急帝王切開での出産時でした。
実はその後、耳鼻科での全身麻酔科での入院手術とレーシックの外来手術でも手術給付金と入院給付金を受け取ったっけ・・・。
その時は「お金が入ってラッキー♪」で終わりました。
私の場合はお産に耳鼻科疾患・レーシックという、悪性の病気ではなかったから。
いつ仕事に復帰できるかもわかっていた(育休はMAXで1年、耳鼻科入院は1週間、レーシックは3連休を使って週末だけで済みました)し、当時はまだ経済的な不安を抱えるような状態ではありませんでした(夫もいたし、子供も1人、持病もコントロールできていた)から。
だから「ラッキー♪」で済んだのです。
しかし、もしいつ仕事に復帰できるかわからないという状況だとしたら、どうなるでしょうか?
先の見えないことだからこそ、人は不安になります。
だからこそ、保険に入ろうと思うのです。
では、「もしも」の時の危機管理が万全で、不安がなかったら?
・・・保険は不要ですね。
生命保険というと、過去の私のように「社会人なら入っておくもの」と、光熱費と同様に支払うべき固定費と思っている人も、世にはたくさんいます。
しかし、本当はもしもの時に困らない人には、保険は不要なのです。
ですから、本来家族構成や病気の有無、資産、雇用形態によって保険が必要かどうかは人それぞれ違うはず。
それを一律「社会人なら」と、ろくにライフプランを立てずに加入するのはおかしな話。
入るのが前提にあって、何に入ろうかと考えているのですから。
生命保険に頼らず、もしもに備えることは可能?
「もしも」の時のために入るのが、生命保険。
でも、あらかじめ有事にいつでも対応できるように危機管理をしている人なら、生命保険に頼らなくても大丈夫。
では、それぞれの費用に対し、どう対策をとっておけばいいのでしょう?
上に挙げたもしもの時に困ることについて、順に考えていきましょう。
1.生活費
障害を負ったり仕事ができない状態が続いたり、一時的に仕事ができない場合は、障害年金・傷病手当金・生活保護といった公的なセーフティネットによって救済処置があります。(自営業者や専業主婦には適応のないものもありますので、注意が必要ですが。)
ただし、これらのセーフティネットで保障されるのは、現在の生活水準ではありません。
最低限の生活水準を保障しているにすぎませんから、現在の生活水準の高い人、言い換えると生活コストの高い人は、これだけでは生活できません。
逆に、普段から生活を最低限度にしている人は、いざという時は公的なセーフティーネットで乗り切ることができるのです。
しかし、生活水準の高い人であっても、充分な資産がある場合や自分が働かなくても収入を得る仕組み(俗に言う不労所得ですね)を持っている人も、生命保険に頼らずにもしもの状況を乗り切ることができます。
2.教育費
教育費も、各家庭における価値観によって何千万単位での差が出る支出です。
どのくらい我が子の教育にお金をかけるかは、親の人生観・金銭感覚が反映するからです。
義務教育以外にかかるものはお金をかけない家庭もあれば、幼稚園や小学校から私立のエスカレーター式に入れる家庭もあります。
スポーツや習い事に、膨大なお金をかける家もあります。
しかし、この教育費に関しても考えようによっては生命保険に頼ることなく乗り切ることが可能なのです。
まず、公的な機関を最大限活用すること。
それから、学校外教育費を抑えること。
子供にかかる衣類や学用品を、できるだけコストカットすることです。
具体的な方法としては、
- 公立学校で高校(できれば大学も)まで進学する
- 図書館や公民館、公的サービスを活用する
- ネットを活用して、塾にかかる費用をかけずに学校外教育を受ける
- 自治体のイベントに積極的に参加して、格安レジャーで済ませる
- フリーマーケットやオークション、リサイクルショップを活用して、衣類などのコストを下げる
- 子育てネットワークを広げておき、子育てを大勢で担う
(困ったときに預かってもらう、サイズアウトした物を譲り合うなど)
このように、まず教育に関する費用を落とすことが1つです。
そしてもう一つは、あらかじめ教育にかかる費用を先に貯めておくこと。
子供1人に高校から大学まで1000万までと決めて、それを小学生の間に貯められたら、中学生以降の教育費にかかる不安はありませんよね。
大学進学費用は、かけようと思えばいくらでもお金をかけられます。
しかし、いざという時のことを考えたら、容易しておいた1000万から高校の費用と大学受験にかかる費用を引いた残りで、行けるところを本人に選択させればいいのです。
(ここで安易に奨学金・・・と考えるのはオススメしません。足りないときの最終手段としてとっておきましょう。)
このように、お金をかけない・現金で貯めておくということができれば、教育費に関するもしもの時の不安はかなり減ります。
もちろん、子供のいないDINKSの場合は教育費に関する不安はゼロですし、既に子供が独立してしまった場合もゼロですね。
3.住宅費
生涯かかる住宅費は、持ち家か賃貸かという選択による違いが、大きく出ます。
しかし、これも1・2同様に、よく考えてみれば保険に頼らずになんとかなるかもしれません。
まず、親からの家がある場合、自分にもしものことがあっても、その家に住み続けることは基本的には可能ですね。
固定資産税や修繕費はかかりますけれど。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合。
住宅ローンを組む際には、通常は団体信用保険というものに加入します。
もしものことがあって収入が途絶えた場合には、残りのローンはチャラにしますよというもの。
この保険が適応されれば、大黒柱である夫や父親が亡くなっても、遺族はその家にローンを払うことなく住み続けることができます。
ただし、ここで考えておくべきなのは、この団体信用保険を過信しないこと。
これが適応されるのは、亡くなったときや本当の高度障害者になった時だけです。
私がもしヘルニアが悪化して、歩くのがやっとという状態になったら、本業である看護師としての職はかなり厳しい状態になります。
しかし、ヘルニアは障害者とは認定されませんから、収入がないのに住宅ローンを払い続けなくてはならないのです。
賃貸の場合は、年金生活になったとしても、一生家賃を払い続ける必要があります。
しかし、現在10万の家賃なら半分の5万の物件に変更することもできるし、公的な市営住宅などに入れば、収入に応じた家賃になります。
これらの想定しうるパターンのうち、自分に潜むリスクは何かを考えましょう。
もし十分な貯蓄があれば、自宅にかかる固定資産税やもろもろの維持費を払うことができますし、住宅ローンを一括で返済できます。
また、1の生活コストを下げることにもつながりますが、田舎に住むというのも一つの危機管理です。田舎なら持ち家を選択するにしても価格は抑えられますし、賃貸ならば地域によっては数万円で2DKくらいの家族で住める間取りが借りられます。
ね?住居費に関する不安も、場合によっては保険に頼らずに済むかもしれませんね。
4.介護にかかる費用・労力について
自分の親にもし介護が必要になったら、どうすればよいでしょうか?
これは介護度にもよりますし、予測するには限界があります。
A.施設入所
B.グループホーム入所
C.自宅で介護しつつ、デイサービスやショートステイサービスをフル活用する
D.自宅で自分が介護する
費用の面で考えると、Aが一番負担は大きくて、Dが一番負担は小さいですね。
しかし、労力で考えると全く逆転します。
介護は24時間ですから、Dが一番介護する側の負担が計り知れません。
Aならば、自分の睡眠時間まで削るということはありませんから。
これらの選択肢が存在することを知らなければ、介護にかかる費用と労力に関しての将来設計はありません。
国は現在、Cを積極的に進めています。
そして、ある意味これが一番の理想だと私も思います。
Dが一番ではないんです。
これは、介護をする側の人の生活が守られないから。
もし自分がある日突然、親に介護が必要になってAからDのどれかを選択しなければいけなくなったとき、どうしましょう?
十分なお金があれば、完全に自費(介護保険の適応なく)でも納得のいく施設に入所することもできます。
お金がなくても、兄弟や親戚が近くに集まっていて日頃から協力しあっている家庭では、Dで乗り切ることができます。
お金も貯めていない、頼れる親族もいない・・・そうなると、生命保険の出番となってくるでしょう。
実際、近年介護にかかる費用を対象とした保険商品も、増えて来ましたね。
1から4でお伝えしてきたように、場合によっては生命保険に頼らずに乗り切ることができる、ということをまず知らなくてはいけません。
もしもの時に活用できる公的サービスやセーフティネットは何か、自分の家にかかるリスクは何か、自分が今の給料を稼げなくなったどうするのか、自分の周りには助け合える人的資源がどれくらいあるのか・・・これらを自分で考えなくては、保険を検討することはできないのです。
生命保険というのは、ライフスタイルや人生設計、職業意識、人付き合い・・・様々な要素を自分の生活に組み込んで考え、それでも対応できないことに対して加入するもの。
ですから、私のように「社会人になったから保険の1つでも」と入るのは、まったく筋の通っていない話なワケ。
私の場合は保険金の給付を何度も受けたので、全く無駄ではありませんでした。
しかし、世の中にはただ勧められるままに加入して無駄なお金を払い、それでいて貯蓄が進まない・・・という家庭も多くあります。
それでは本末転倒ですね。
生命保険に加入するかどうか、何を選ぶかどうかを考える前に、家族に「もしも」のことがあった場合、どんなセーフティネットがあり、どのような選択肢があるのか、何に対しては自分では対応できないのかを考えること。
これが、保険に関する最初の一歩と言えるでしょう。