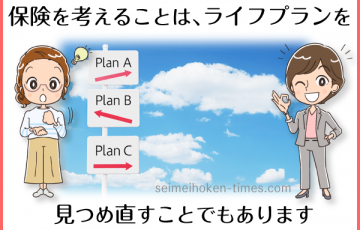子供1人に教育費は1000万!?
子供はかけがいのない宝ものです。
親となったからには、子供に十分な教育を受けさせてあげたい、好きな道に進ませてあげたい、誰しもそう考えることでしょう。
十分な教育を受けさせるためには、好きなことをさせてあげるには、一体いくらかかるのでしょうか?
教育費は、いくら用意したら安心なのでしょうか?
よく耳にするのは、「子供1人に1000万円」という金額ではないでしょうか。
今回は、教育費に関連する生命保険についてお伝えしましょう。
教育に関する選択は、0歳から始まる
人は、自分のわからないことに対して不安を抱くものです。
では、私達が普段抱く「教育費」とは具体的に何のことなのか、考えていきましょう。
教育費は、生まれた瞬間から発生します。
最低限の教育費には、普段の食費や洋服代、乳幼児ならミルクやオムツがかかりますね。
これは生きていくために当然かかる費用であり、親の義務です。
(これらの義務を果たさない、つまり必要な食べ物や衣類を与えないのは、虐待です。)
しかし、私達が不安を抱いている「教育費」というのは、これらの生活必需品を買うためのお金ではありませんよね。
そこで、まず先にこの表をごらんください。
保育園(もしくは託児所)から始まり、どのような選択肢があるのかをまとめてみました。
<教育費=学校教育費+学校外教育費‼の図>
保育園から始まり、大学まで、様々な道があります。
特に大学は学部・学科でも大きな違いになりますね。(特に医学部・歯学部など)
また、メジャーではないにしても中学から全寮制の学校に入れたり、高校・大学で留学させるといった家庭もありますから、選択肢は数えきれないほどあるのです。
私は、息子を生後8か月から認可保育園に預けて職場復帰しました。
毎月65000円でした。
この金額が高いか安いかは地域にもよるのでしょうけれど、私の住む地域では高い金額に入ります。
保育料は年齢を重ねるにつれて安くなるので、最終学年(年長)では月24000円でした。
0歳から6歳の保育料の総額は軽く250万円を超えています。
この時点で、年少から幼稚園に通った家庭との間では、既に100万単位のお金の差が出ます。
私は保育料に加え、実家の母に保育園の迎えと夕食を頼んでいたので、毎月数万円実家に入れていました。
保育料と実家への仕送りだけで、小学校入学前に500万円近くかかりました。
保育園に6年通ったあと、今度は義務教育が始まります。
我が家は、地元の公立小学校に入れました。
保育園時代よりも、経済的な負担はものすごく軽くなりました。
もしここで、私立という選択をしたらどうなるでしょうか?
小学校生活は6年ありますから、最低6年間はその学費が続きます。
小学校入学時に私立という選択をとった家庭は、中学・高校も私立と続いていくことが多いので、実際は9年・12年・・・と私立の学費がかかることになります。
私立の学校に入学した場合、学費だけではなく全てが公立よりも高くなります。
制服だけをとっても、公立よりも相場は高いですね。
では、公立だけでいけばいいじゃないと思いますか?
高校の修学旅行は、公立でも海外旅行が主流となってきています。
パスポート代に現地でのお小遣いと、昔とは修学旅行にかかる費用も桁が違うのです。
公立に入れたから安心、といえないのが現代の教育費事情です。
そして大学は、親にとって最大の難関です。
遠方の大学を複数受けると、入学前の受験だけで何十万もかかります。
最終学歴もここで決まりますし、就職・その後の年収にも影響するので熱が入るのも当然です。
こっちが主役!?学校外教育費
いい大学に入学させるために、いい高校に入る。
そのために小中学生の頃から学習塾に通う・・・教育費は、学校でかかる費用だけではありません。
上の表にもありますが、「教育費=学校教育費+学校外教育費」なのです。
学習塾を始め、学校の外での活動は教育費の中でも大きな負担となっています。
むしろ、義務教育の間は学費そのものがゼロなので、こちらの方がお金はかかります。
表にもある通り、学校外教育費は大きく分けて3つ。
- 学習系(塾・英会話・公文・そろばんなど)
- スポーツ系(サッカー・野球・スイミング・バレー・テニス・卓球・武道など)
- その他(書道・ピアノ・バレエなど)
更にちょっとマイナーなところで、親の趣味や好みをそのまま子供に・・・となると、ダンスやフィギュアスケート・ロードバイク・スノーボード・サーフィンなど、どんどん幅が広がっていきます。
毎月の月謝だけではなく、学習塾なら夏季講習や冬期講習、模試なども含めると、年間何十万もかかる出費となります。
スポーツ系なら、大会や合宿・大会遠征などで、一度で何万円ものお金がかかります。
個々の競技に必要な道具やウエア―も、自己負担です。
学校の成績に直接影響しないスポーツや文化的な教養に、どこまで時間とお金をつぎ込むか・・・ここは教育費の大きな分かれ道です。
小学生の頃からサッカーに打ち込んできた子供が、高校はサッカーの強豪校に入りたいと言ったら?
それが私立ということもありえます。
場合によっては、下宿が必要な遠方の高校かもしれません。
でも、お金がなければ、行かせてあげられませんね。
親の懐具合でパフォーマンスや進路が変わってしまう・・・それが、学校外教育費の怖いところです。
親なら、子供のやりたいことはやらせてあげたい。
でも、小さいうちに頑張り過ぎて、肝心の大学受験のときに家計が底をついていたのでは、話になりません。
どういう選択を子供がとるかはわからないけれど、ある程度のところまでは対応できるように、備えておきたいものですよね。
お金に色を付けてしまえ!それがこども(学資)保険
子供が何をやりたいと言い出すか、どこの大学に行きたいと言い出すか・・・子供の選択によって教育費が何千万も変わってくるかと思うと、ヒヤヒヤしますね。
私達親は、一体どうやって教育資金を用意したらよいのでしょう?
そこで、主に大学でかかる教育費に備えるためにあるのが「こども保険」です。
こども保険は学資保険とも呼ばれます。
大人の病気や怪我に対する備えとは違い、はっきりと教育資金に対する備えとして売りだされている商品です。
教育費は、子供の個性や希望によっていくら必要になるか、想像できません。
でも、確実にお金のかかる「時期」だけははっきりしています。
いくらかかるかはわからないけれど、7歳の年の春には小学校に入学するし、13歳には中学校、16歳には高校で、19歳には大学に入学するのです。
大きな脅威ともなる教育費の難関、高校までには15年間、大学では18年の期間があります。
その時間を味方につけて、将来に備えた教育費を作りましょう、というのがこども保険です。
ここで、自分で積み立てれば生命保険に入らなくてもいいのでは?
そう思ったあなたは、スルドイですねぇ。
必ずしも生命保険に入る必要はありません。
しっかり貯められるなら。
仮に、生まれた年から毎月1万円ずつ積み立てたとします。
月1万円×12か月×15年=180万円が高校入学までに貯まりますね。
大学入学に合わせるなら、月1万円×12か月×18年=216万円になります。
これに子供手当を合わせたら、
0~3歳:月15000円×12か月×3年=54万円
4~15歳:月10000円×12か月×12年=144万
(子供手当はその時の政策によって変わりますので、将来を約束されたお金ではありません。)
毎月1万円の積み立てと子供手当で、大学入学時までに400万円ほどの貯蓄になります。
これだけでも、結構な金額になりますね。
けれども、銀行口座に入っていると思うと、「今月ちょっと苦しいな・・・」という時や、「サッカー合宿でお金がかかるのよね」という具合に、簡単に下ろすことができてしまいます。
生命保険にしてしまえば、簡単には使えないようになります。
そうすることで、「将来の教育資金」と生活費をはっきりと区別するようになるので、確実に18歳までに目標額を貯めることができます。
親というものは、こうして「子供用」としてしまうと、「教育資金に手を付けてしまう情けない親になりたくない!」という心理が働きますので、ほぼ強制的に貯めることができるのです。
もし大学入学時に216万円では足りないと思えば、毎月の保険料を上乗せして300万円にも400万円にもすることができます。
お金に色はついていないといいますが、あえて「これは子供用」と色を付けてしまえ!というのが、こども保険なのです。
コツコツ貯めるのが苦手な人には、いい方法ですね。
こども保険には、どんな特徴があるの?
では、もう少しこども保険について説明していきましょう。
こども保険は、ただ決まった年までに決まった金額を貯めるだけではありません。
こども保険には、積立預金にはない特徴があります。
【1】親に「もしも」のことがあった場合には、保険料の払込が免除される
【2】わずかではあるが、定期保険よりも利率が高い
【3】死亡保険がついている
私は個人的に、こども保険に加入する最大のメリットは【1】だと思っています。
これは、もし親が亡くなってしまってもその後の保険料の払込が免除され、それでいてお祝い金(満期保険金)は満額受け取れるという契約なのです。
最低でも、大学受験や大学入学にかかる費用はまとまった金額を用意できる、ということです。
親が生きていても、亡くなっていても。
親が亡くなって積立を辞めてしまった場合には、そこから貯蓄額が増えないことを考えると、ありがたい制度と言えますね。
子供が小さいうちだと、少額のうちに積み立てがストップしてしまいますから。
【2】は、普通に銀行の定期預金に預けておくよりは多少なりとも利子がついてくるので、お祝い金にその分がプラスされてきますよ、ということです。
しかし、18年預けても20万円とかその程度なので、おまけくらいにとらえていた方がよいでしょう。
【3】は、メリットと言えるかデメリットと言えるかわかりません。
こども保険は、子どもの医療費や死亡時のための費用としてとらえている親は、ほとんどいないでしょう。
子供には、医療費はあまりかからないからです。(保険診療の分は)
それに、子供が亡くなったからといって、自分達の生活費に困るということはないので、死亡保障を付ける意味はあるのか・・・というところですね。
でも一応、子供に「もしも」のことがあった場合には、葬式代などにあてることができます。(考えたくもありませんけれど)
その代り、この死亡保障があるが故に利率が低くなってしまう、ということは覚えておきましょう。
(保険会社も慈善事業ではありませんから、当たり前ですね。)
これらを考えると、子供保険に入るメリットは【1】に尽きる、と思っています。
教育資金を貯める金融商品は、子ども保険とは限らない
こども保険というと、生まれたらすぐ入れるものというイメージがあるかと思いますが、5歳だろうと10歳だろうと入ることはできます。
ただ、時間という恩恵を受けるためには早い時期から入るのが望ましいですし、最近では生まれる前から加入することができる子ども保険もあります。
ここで少し難しい話をしてしまうと、実はこども保険は「生まれたとき=加入どき」とは限りません。
こども保険の利率は加入時に決まってしまうので、それがちょうど利率の高いとき(近年高いということはありませんけれど)ならいいのですが、低いときに入ってしまうと、その利率がその後18年間続いてしまうのです。
また、一度こども保険に支払った保険料は、満期になるまで引き出せません。
利率の低いこども保険に入れて資金を眠らせてしまうのであれば、別の運用方法で貯めるという手もあります。
投資信託なら元本は保証されませんが、運用次第では18年で20万円なんてレベルではなく、もっと増える可能性があります。
最近では千円単位の少額から投資することもできますので、これらを上手に使ってもいいかもしれません。
また、生活防衛費とは別に自分(親)が「〇〇のための教育用」として子供1人に対して1つの死亡保険に加入しておくのもいいかもしれません。
10年払込にするために月2万円ほどの保険料にして、500万円の死亡保険をつけておくとします。
中・高と教育費がかかるようになる前に、保険料を払い終えることができます。
その後は寝かせておくだけで利率が上がり、18歳の時点では解約返戻金が100%(元本を上回る)を超えるようになります。
こども保険はその後の保険料の払込がない代わりに、当初設定した金額しか受け取れません。
死亡保険なら、親に万が一のことがあったら死亡保険金を受け取り、無事なら解約返戻金を受け取ることができるのです。
子供にかかる費用は、キリがありません。
かけようと思えば、いくらでもかけられるのです。
今回は、教育費をはじめ、こども保険・その他金融商品についてお伝えしてきました。
でも、子育てで大切なのは、いくら残すか・いくらかけるかではありません。
どれだけ愛情を持ってわが子に接するか、なのです。
愛情はプライスレス。
いくらかけてもタダですから(*^-^*)