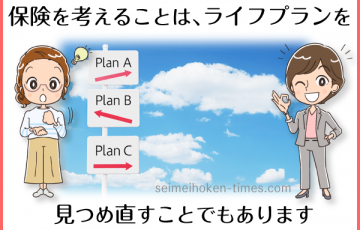高齢者を支える「介護保険」とは
「介護保険」と聞くと、あなたは何を思い浮かべるでしょうか?
おそらく、公的な介護保険ではないでしょうか。
実は、介護保険には公的な介護保険と、民間の介護保険の2種類があります。
高齢者がデイサービスや施設入所などのサービスを受ける際に必要となるのが、公的な介護保険です。
介護保険制度は、高齢社会と核家族化の進む日本において、介護が家族の手でされることに限界が生じてきたことから、2000年に始まりました。
国民が介護保険料を支払い、介護が必要になったときには、介護度に応じて1割の自己負担で各種介護サービスを受けられるものです。
介護保険制度では、必要な人に必要なだけのケアを提供するために、介護が必要な度合い(日常生活の自立度)によって、介護度を付けます。
そして、この介護度によって受けられるサービス、入居できる施設が決められます。
介護保険制度についてはここでは説明しきれないので、厚労省ホームページを参照してください。
介護保険制度の経緯から改正点まで、かなり詳しく説明されています。
<公的介護保険制度の現状と今後の役割>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/201602kaigohokenntoha_2.pdf
一方で、介護の現場は人手が不足しており、いくらお金があっても満足いくサービスを受けられるものでもありません。
施設に入所させたいと思っても空きがなく、都市部の高齢者が住所を変更して地方で入所せざるをえないなど、大きな問題となっています。
介護はいくらかかるのか?
公的な介護保険では、利用した介護サービス(入浴サービスや、デイサービスなど)の料金の1割を支払います。
(高所得者は2割負担になります)
介護保険で様々なサービスを受けても自宅介護が困難になり、グループホームや施設入所する場合には、入所時に支払う一時金は数百万かかるのが一般的です。
中には、1000万円近くかかる施設もあります。
入所後も、毎月の入所費用がかかります。
オムツ代など別途実費で請求されるものもあり、これも施設入所を選んだ場合の悩みのタネです。
個人の年金額にもよりますが、純粋に年金だけで毎月払いきれる施設は、ほとんどないのが実状です。
本人の年金と預貯金だけでは施設への支払額が足りない場合、現役世代である子供達が払うことになります。
しかし、子供達も住宅ローンに教育費と、四苦八苦している状態です。
毎月10万・20万と親の施設費用を払い続けられる人は、なかなかいません。
この経済的な負担を担えない子供世代は、どうするか?
非常に介護度が高くなっても、在宅介護をせざるをえません。
しかし、在宅でも介護にはお金がかかります。
介護度に応じたサービスだけでは足りない場合には、全額自己負担でヘルパーを雇ったり、デイサービスやショートサービス、訪問入浴などを受けることもあります。
また、高齢の両親を自宅で介護することによって、働きに出られなくなっている人もいます。
本来なら働いて得ていた分の収入も考えると、本当に介護は経済的な負担が高いのです。
これが何年続くのか、誰にもわかりません。
先がわからないからこそ、不安になる。
それが人間というものです。
昔と違い、医療は進歩しました。
そして、「ピンピンコロリ」と亡くなる人も減りました。
日本人の平均介護年数は、10~15年と言われています。
しかし、これはあくまでも平均。
親や自分がどうなるかは、わかりません。
もし自分に何かあったら、家族は自分の介護費用を払うことができるのか・・・そんな不安からうまれたのが、生命保険会社による民間の「介護保険」なのです。
生命保険の「介護保険」は、給付条件に難アリ?
民間の介護保険はまだまだ新しい部類の保険で、若いうちから要介護状態になった時を見据えて保険料を払い込んでおくものです。
周囲で実際に受け取って「助かりました!」「入っていてよかった!」という声を聞いたことがなく、私自身はまだ加入を検討したことがありません。
生命保険として介護保険の恩恵を受ける人が出てくるのは、まだもう少し先なのかもしれませんね。
老後の費用については個人年金保険(個人年金保険の基本を理解しよう!)でもお伝えしましたが、いろいろな備え方があります。
現金を貯めるだけでなく、個人年金に加入してもいいし、投資信託でコツコツ積み立てて老後に解約するのもいいですね。
死亡保険の解約返戻金を、施設入居費用に充てる方法もあります。
これらの方法ではなくて、あえて介護保険にする必要があるのか、検討すべきでしょう。
個人年金は一定の年齢になったら、決まった方法で現金を受け取るものです。
元気だろうと、寝たきりだろうと、時が来れば受け取れます。
(死亡後も受け取れるかどうかは、契約によって異なります。)
その代り、一定年齢にならなければ受け取ることはできません。
介護保険は、保険商品によって給付条件に大きな差があります。
その条件は個人年金のように年齢ではなく、介護度や日常生活の自立度を基準とします。
公的な介護保険制度による介護度と連動しているものもあれば、保険会社独自の基準を設けているものもありますので、注意が必要です。
連動タイプの場合には比較的「要介護2」が条件となっていることが多いのですが、このラインに届かなかった場合はどうなるでしょうか?
食事やお風呂など、生活する環境をそろえてもらえれば日常生活の自立している人は、「要支援」にしかなりません。
それまで1人暮らしをしていたけれど、買い物や食事のしたく、お風呂の準備、洗濯ができなくなって困っているという場合でも、要介護2までは給付金を受け取ることができません。
また、介護度と連動しないタイプの場合では、保険会社の定めた「所定の状態」が給付条件となります。
単純に日常生活の自立度だけではなく、180日介護の必要な状態が続くなど、一定期間の継続が条件となることもあります。
ヘルパーを頼むお金が欲しい!
施設入居費用が欲しい!
ケガをした間だけ、入浴サービスを受けたい!
こんなときのために若いときから保険料を払ってきたのに、いざというときに受け取れない。
他にも、いろいろなリスクが考えられると思います。
どの程度の介護度が何年続くのか、いくら介護費用が必要なのかは、本人すらわかりません。
介護が長期間に及んだら、払いきれるか自信がない・・・。
介護費用は想定できないからこそ、どう備えたらよいかわからないのです。
「長生きリスク」にどう備えるか
個人的には、介護保険は死亡保険や医療保険ほどおススメ度の高い保険とは思っていません。
不確定要素が大きいものに、何年・何十年とお金を固定してしまうことになりますから。
現金なら融通がきいて、何にでも使うことができます。
介護保険は、「長生きリスク」に対応する保険商品です。
元気でないのに長生きした場合の「もしも」に備えるもの。
介護保険には、給付金の受け取り方法が一時金のみもしくは年金形式のみ、一時金と年金の併用があります。
年金形式の場合は、長く生きる方がトータルの給付金額は多くなってお得です。
逆を言うと、長生きしなかった場合には保険料を毎月頑張って払っても、払い損となる可能性があります。
解約返礼金や死亡保障のないものもあるので、元本割れを起こすことがありえます。
ここが、必ず死亡した時に受け取れる死亡保険との違いでしょうか。
もし50代になって老後が心配になって・・・と加入を検討する場合、短期間で払い込まなければならないので、毎月の保険料は高くなります。
また、長生きする分女性の方が保険料は高くなります。
確実に受け取れるかわらかないものに、どれだけのお金をかけるべきでしょうか?
老後費用は、教育費以上に先が読めません。
教育費ならある程度は年齢で決まりますが、老後費用については何十年単位にもなりうるからです。
年金だけに頼れないこれからの時代には、現金やその他不動産、投資信託などの資産運用、生命保険・・・長生きリスクにどう備えるのか、十分な検討が必要です。
1つ言えるのは、「1つのカゴに、リスクもお金も盛らない」こと。
もし全力投球で払い込んできた生命保険で給付条件を満たさなかった場合、目もあてられません。
もしかしたら、毎月5000円のコツコツ貯金があなたを救ってくれるかもしれません。
23歳の就職時から、毎月5000円コツコツ貯めたら・・・利子をゼロとしても、65歳で252万円、毎月1万円なら500万円が貯まります。
これだけあれば、施設入所の一時金もなんとか払えるでしょう。
先のことなんて、誰にもわかりません。
どこで納得するか、ではないでしょうか。
将来(老後)を考える際には、長生きリスクにいくらかけてどこまで備えるか、自分自身でラインを引く必要があります。
老後費用って、考え始めたらキリがありませんね・・・。
でも、その選択肢の一つとして介護保険を考えてみるのもいいかもしれませんね (*^-^*)