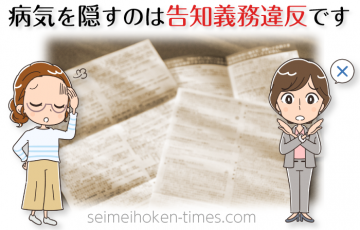保険代理店の仕事は、保険商品の説明にあらず
知り合いの生命保険の営業さんが、こんな話をしていました。
「保険の説明の前に、話さなければならないことが多すぎる」と。
生命保険は、企業の場合は社員への福利厚生や事業承継・相続税対策などで加入することもあります。
しかし、一般の人が加入を検討する場合は下のどれかの場合に備えてのことでしょう。
<生命保険に加入するのは、なんのため?>
- 病気にかかったときの医療費
- 病気やケガによる就労不能状態に陥った場合の生活費
- 子どもの教育費
- 死亡もしくは高度障害状態になったとき、遺された家族の生活費
- 介護が必要になったときのための介護費用
この全てを別々の生命保険に加入するとなると、保険料だけでものすごい金額になってしまいます。
もしもの事態に備えすぎて、今の生活が成り立たなくなってしまいかねません。
そこで必要になるのが、公的社会保障の知識や各種制度の情報です。
医療や介護、遺された家族のための制度には何があるのか。
教育費を自己資金だけで捻出できなかった場合に利用できる貸付制度は、何があるのか。
具体的には、遺族年金や高額療養費、指定難病に対する医療費助成制度、介護保険などでしょうか。
「公的な社会保障を知らない」~よくある生命保険のムダ05~でもお伝えしていますが、もう一度復習してみましょう。
<病気やケガで働けなくなったときの制度>
高額療養費制度 (全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき)
傷病手当金 (全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき)
療養費 (全国健康保険協会 医療費の全額を負担したとき)
<障害を負った・一家の大黒柱が亡くなった場合の制度>
障害年金 (日本年金機構 障害年金)
遺族年金 (日本年金機構 遺族年金)
生活保護 (厚生労働省 生活保護制度)
<その他>
介護保険 (厚生労働省 介護保険制度の仕組み)
ひとり親家庭 (厚生労働省 ひとり親家庭等の支援について)
教育費 (日本政策金融公庫 教育一般貸付)
これらの制度によってどのくらい生活を支えてもらうことが可能なのかを把握した上で、生命保険でどのくらいの保障額を設定するべきなのか、どのような商品を選択すべきなのかが決まります。
逆に考えると、前提となる条件を知らないと、いくら保険の営業が熱心に商品を勧めたところでピンとこない。
だから、商品説明の前に基本的なレクチャーが必要になるのですね。
私自身、恥ずかしながら最初に加入した生命保険は、内容も全くわからずに契約した養老保険でした。
マイホーム購入に出産・・・となって初めて、自分で生命保険を考えるようになりました。
そのときも、どうやって保険を選んだらよいかどころか、医療従事者であるにも関わらず社会保障制度についても知らないことばかりでしたね。
そして、「もしも」のときを考えるにあたり、保険代理店の営業さんに生命保険の基本から教わったわけです。
冒頭の「保険の説明の前に説明することが多い」という嘆きを聞いたとき、自分も10年前はそうだったなぁと思ったのでした。
10年経ってようやく、十分ではないにせよ少しは知識がついてきたなあと思えるようになりました。
契約前に、これだけは勉強しておこう
私自身は生命保険も金融知識も全くない、なんとも情けない20代を過ごしていたわけですが。
これから生命保険を検討したり新しい家庭を築くという若い世代の人達には、もっともっとお金について勉強してから行動して欲しいなあと思います。
お金のことは、学校ではほとんど教えてくれません。
だからこそ、自分で情報収集して勉強する必要があるのです。
10年前よりもネットで得られる情報は多くなりましたし、公的機関のサイトも充実していますから。
緊急事態が起こったとき、生活する上で必要となるお金=必要保障額はどうやって計算すればよいのでしょうか?
まずは過去1年、無理なら最低3か月の家計の収支がわかるものを用意します。
そして、自分がいくらで毎月生活をしているのか計算しましょう。
それから、受けられる公的保障の金額を調べます。
例えば遺族年金なら、遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、遺族基礎年金の場合は子ども1人なら年1,003,600円(2018年2月現在)です。
(遺族年金については<専業主婦の生命保険~わたしと我が家はどうすべき?~>でもお伝えしていますので、参考にしてくださいね。)
これに加え、会社からの退職金や弔慰金があると思います。
マイホームのローンを夫名義で組んでいる場合、団体信用生命保険に加入していれば夫が死亡したらローンは実質チャラになります。
預金残高だけではなく、全ての金融資産を洗い出しましょう。
<もしものとき、いくらあれば安心? 必要保障額を計算しよう>
【1】預金額
全ての預貯金の総額
現時点で加入している生命保険の解約返戻金
【2】受け取れるお金
公的社会保障(遺族年金、老齢年金、高額療養費など)
退職金・弔慰金
団体信用生命保険
現在加入している生命保険の死亡保険金・給付金
【3】必要生活費
(子どもが独立するまでの生活費+教育費)×年数
子どもが独立後の自分だけの生活費×年数(余命)
必要保障額=【1】+【2】-【3】
専業主婦家庭の場合は、妻がフルタイムで勤務すれば、その分必要保障額を下げることができます。
現在妻がパート勤務なら、フルタイム勤務で得られる収入との差額分は必要保障額を下げられます。
現時点の備えで足りないものを生命保険で補うのか、それとも今から貯蓄ペースを上げて対応するのか、老後に老齢年金で不足する分に関してはiDeCo(イデコ)個人型確定拠出年金で積み立てるか・・・選択したくさんあります。
これらを組み合わせて備えてもいいですよね。
ただし、「積み立て系」は時間を必要としますから、数年以内に起こる緊急事態に対応するのは難しいでしょう。
そこで、「どの割合を生命保険で備えるか」というラインをあらかじめ立てておく必要があります。
保険の営業マンはファイナンシャルプランナーの資格を持っていることが多いので、ある程度の基礎知識やNISA・iDeCoなどの話もしてくれるとは思います。
しかし、彼(彼女)らの仕事は生命保険の新規契約や更新が目的ですから、相談するのは生命保険で備える部分に関してどんな商品がいいかに集中すべきだと思います。
保険代理店は契約によって収入を得ているので、契約さえとれればいいというスタイルの人も存在します。
一方で、地元密着型の親子2代で営んでいる代理店などは、一生のお付き合いを念頭にして契約を勧めたりします。
大手家電量販店
町の電気屋さん
ネットショップ
の違いのようなものでしょうか。
なんでも保険屋さんで相談すればいいものでもないし、どこまで個人の生活に密着してトータル的なアドバイスをしてくれるかは、その代理店のスタイルによっても違います。
ですから、まずは自分で情報収集し、最低限のお金に関する知識をつけておくことが大切です。
情報を得て知識をつけることで、無駄な商品や必要保障額に満たない商品を契約することも避けることができますね。
生命保険はこの先何年・何十年という付き合いになりますし、総払込額は何百万円に及ぶこともあります。
保険選びは、最初が肝心です。
しっかり勉強してからじっくり選んで欲しいですね。
何から勉強していいかわからない・・・という場合は、ファイナンシャルプランナー3級の勉強をしてみるのもおススメです。
一般家庭における家計管理に必要なことが、幅広く学べるはずです。
ネットで簡単!お役立ち情報
今の時代は、少し検索すればネットでたくさんの情報を得ることができます。
中には不確かな情報もありますが、少し意識して調べるだけで素人だって生命保険の商品内容や、銀行の金利を調べることもできます。
もし何か知りたいことがあったときにどこを見ればわかるか知っていることは、一つの保険です。
知っているということが、それだけで何万・何十万円の価値に匹敵するのです。
日本にはいろんな制度がありますが、黙っていても受けられる制度はありませんからね。
つまり、知らないことには申請できないし、受け取れないのです。
私が普段活用している情報源のうち、ネットで見られるものをご紹介しましょう。
ほとんどが公的機関やそれに準ずる団体によるものなので、情報の真偽を気にする必要がなく安心です。
<~あなたの困った!を解消するお役立ちサイト~>
厚労省
日本年金機構
全国健康保険協会
知るぽると(金融広報中央委員会)
生命保険文化センター
日本損害保険協会
日本FP協会
日本政策金融公庫
これらのサイトで調べてみたけれどもっと詳しい内容を知りたいときや、具体的な相談・手続きをとりたい場合はどこに行けばよいのかあらかじめ知っていると、更に安心です。
お金や生活に困ったときなど、とりあえず何か行動しようという場合に行くべき場所はどこだと思いますか?
市(区)役所です。
母子家庭や子どもの教育に関する相談は、役所内で完結することも多いですね。
介護保険の申請も、まずは市役所です。
場合によってはそこから福祉事務所や年金事務所に相談するように勧められることもあるだろうし、ハローワークが出てくることもあるでしょう。
生活する上で困ったことがあったらまずは市(区)役所に相談してみると、その後の道筋や自分の知らなかった制度について教えてもらえます。
しかし、現実には誰にも救いを求めないで一人で悩みを抱えている人が多いことに驚かされます。
明らかに生活に困窮していたり体が不自由であっても救いを求めず一人暮らしをしている高齢者を、近所の住人が見かねて通報したことで行政が介入を開始する・・・というケースも近年増加しています。
「保険」は生命保険だけではない
いつ・どんなことが起こるかわからないのが人生です。
あとで後悔することのないよう、できるだけの備えをしておきたいですよね。
私自身は、いろんな「保険」をかけています。
保険といっても、生命保険だけではありません。
<もしもの備えは、多岐にわたります>
- 金融に対する知識を増やす
- 預貯金を増やす
- 生命保険に加入する
- 投資信託で積み立てる
- 専門職として(職業人として)のスキル向上に努める
- 家族間で密な関係を築く
- 元夫との(ある程度)良好な関係を維持する
- 地域の人やママ友との連携
- わからないことを聞ける幅広い分野の知り合いを作る
これらのおかげで、私はなんとか持病ありのシングルマザーでもやりくりしてきたし、今も暮らしています。
困ったときにすぐに使える預貯金は大切だし、入院・手術したときには生命保険にお世話になりました。
私が体調を崩したときには、実家の母(だけでなく祖母まで!)に子どもの面倒をみてもらったし、今でも私が仕事の日は姉の家に帰ります。
元夫には、子どもを遊びに連れて行ってもらったりしています。
その間私はゆっくり体を休めることができます。
そして、そこそこの関係を維持することで、毎月の養育費を滞りなく支払ってもらうことができます。
また、私の住んでいるアパートは、目の前が大家さんの家です。
大家さんの孫と息子が、我が家で遊ぶこともあります。
田舎なので、みかんやお菓子といったお裾分けもしょっちゅういただきます。
町内行事のわからないことは、(賃貸契約と関係ないのに)大家さんに教えてもらいます。
保険の営業さんとも公私共にお付き合いがありますから、契約とは別にいろいろなことを教えてもらいます。
他にも法律関係に詳しい人、料理や裁縫が得意な人、学校の先生をしている人・・・たくさんの知り合いから、いろんな情報をもらっています。
これからも、たくさんの人にお世話になると思います。
もちろん、私ができることも(あまりないけど)お裾分けします。
もしもに対する備えというと、生命保険とか預貯金でなんとかしようと思いますよね。
その前に、まずいくらあれば生活できるか把握していますか?
そして、公的社会保障と実際の自分の金融資産でどこまで補うことができるでしょうか。
生命保険を検討するのは、それからです。
家計におけるリスク管理を考えるためには、勉強しなくてはならないことがたくさんありますね。
年金を始めとした各種制度も、これからも変わっていくでしょう。
そのときに判断のもととなる情報・知識を、あなたはどこから得らえるでしょうか?
自分を守るための情報と知識、困ったときに相談できる場所と人。
あなたにはどれだけありますか?
それこそが、本当の「保険」なのかなあと思うこの頃です(*^-^*)