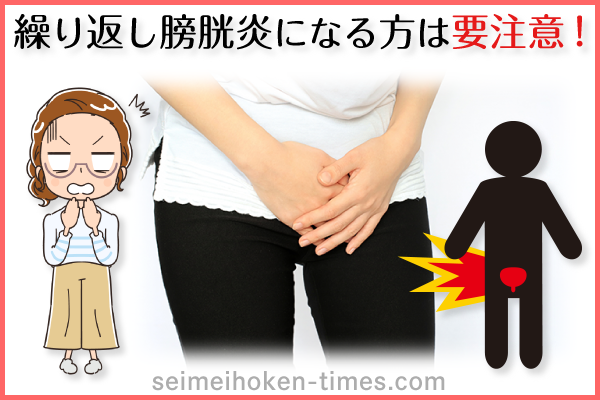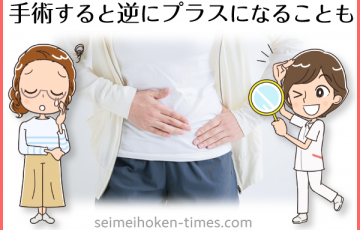膀胱炎ってどんな病気?
膀胱炎は、女性に多い病気です。
病気の中では比較的軽症で、風邪のように単発の受診で済むことが多いので、どうしても軽くみられがち。
おしっこの問題なので、恥ずかしさもありコソッと受診・・・そんなこともよくあります。
しかし、実はたかが膀胱炎、されど膀胱炎。
ひどくなると、怖ーい病気に進行してしまうことがあるのです。
まず、膀胱炎とはどんな病気なのか、ここからお話していきましょう。
膀胱炎というのは、基本的に急性膀胱炎のことを意味します。
外陰部から尿道を通って、細菌が膀胱粘膜に付着&繁殖することで起こります。
本来は、多少の細菌が入っても免疫機能が働くので、膀胱炎にはなりません。
しかし、下の要素が加わると膀胱炎として発症してしまうのです。
<膀胱炎の要因>
- 水分の摂取不足
- ストレス
- 疲れ
- 体調不良(風邪のあとなど)
- 食生活の乱れ
- 排尿の我慢
- 性行為
こういった要因が重なると、膀胱炎になってしまいます。
女性によくあるケースは、販売員などでトイレになかなか行けない人。
お昼休みと終業後しかトイレに行けないため、自然と水分摂取も控えてしまいます。
そうなると、尿として細菌を身体の外に出すことができず、膀胱内で繁殖してしまうのです。
水分摂取と排尿回数が少ないのは今までずっと同じなのに、なぜか急に膀胱炎になってしまった・・・という経験のある人もいるかもしれません。
その時、睡眠不足だったり、いつもより少し疲れていませんでしたか?
それまで1つや2つだった要因に、他のものが加わったことが引き金となって発症してしまうことは、よくあるのです。
さてここで、膀胱炎の要因の最期にある「性行為」、なぜ膀胱炎に関係があるのか不思議に思いませんでしたか?
実は膀胱炎自体、性行為によるものが大きいのです。
膀胱炎は、割と若い女性に起こる病気。
免疫機能の働くはずの若年女性が、なぜ罹ってしまうのでしょうか?
一つは既にお伝えしたように、トイレに行けないなどの職業的な理由があります。
しかし、それ以上に重要な理由として、女性の体の構造によるものがあるのです。
女性は男性と違い、尿道から膀胱までの長さがとても短くなっています。
また、女性の外陰部は、尿道口・膣・肛門が並んでいます。
便をしたあとの拭き方によっては、大腸菌(便に通常含まれている菌)が尿道口から入り込んでしまうのです。
同様に、膣内の細菌も尿道口から入ってしまうことがあります。
性行為のときには更に、陰部付近にいるこれらの菌が尿道口から入り込んでしまう可能性が高くなります。
構造的に尿道が短い分、すぐに菌は膀胱に到達してしまい、結果的に膀胱炎を発症してしまうというわけです。
ですから、膀胱炎は女性に多く、性交渉の比較的多い若い世代に発症する病気なのです。
(高齢者の場合は、水分摂取量の低下や高齢による免疫機能の低下が大きな理由です。)
治療自体は、大量の水分摂取をして大量に排尿し、自然に治ってしまう人もいます。
膀胱炎を繰り返す人の中には、経験的に水をたくさん飲んで、病院に罹らず治してしまう人も多くいます。
しかし、排尿時痛や残尿感などがあるので、なかなかトイレにいくのも苦痛。
医療機関では、通常は抗生剤を処方します。
水分をしっかりとって抗生剤を5日間しっかり飲み切れば、治療のほとんどがそこで終了となります。
適切な治療を受ければ、膀胱炎は怖いものではありません。
逆に適切な治療を受けなければ、もしくは悪化した場合、膀胱炎は怖いものになるのです。
熱の出る膀胱炎は、腎盂腎炎!
膀胱炎はよく耳にする病気だと思いますが、イメージとしては風邪と同じようなレベルではないでしょうか?
確かに、抗生剤を5日飲んで治るのなら、風邪と同じといえば同じ。
しかし、そこから一歩進んでしまった場合には、風邪とは比べものにならないほど、怖い病気になります。
膀胱に入った菌が尿管を逆行して上り、腎臓までたどり着いてしまった場合です。
腎臓には尿を作りだす働きがあり、その中でも腎盂(じんう)という場所が非常に重要な役割を担っています。
そこに細菌が入り込んでしまうと腎盂腎炎(じんうじんえん)という病気になってしまい、膀胱炎とは緊急度も重症度も全く異なってしまうのです。
腎盂腎炎になると、どのような症状が出るのでしょうか?
<腎盂腎炎の症状>
- 38℃以上の発熱
- 背部痛
- 頻尿や排尿痛などの膀胱刺激症状
- 腰背部の叩打痛
- 悪心(吐き気)、嘔吐、腹痛などの消化器症状
膀胱炎では残尿感や頻尿・排尿時痛といった症状がありますが、高熱は出ません。
高熱が出た時点で、腎盂腎炎を起こしているといってよいでしょう。
そうなると何が怖いのでしょうか?
高熱が出ること?
いいえ、そうではありません。
「敗血症性ショック」という状態になることが、怖いのです。
敗血症?
聞いたことがないかもしれませんね。
製薬会社のMSDがMSDマニュアル家庭版で詳しく説明していますので、参考にするとよいでしょう。
敗血症性ショックとは、血液中に菌が入り(菌血症)、それによって血圧が低下してしまうことをいいます。
血圧が低下してショック状態になると、意識が失くなるだけではなく、生命維持にかかわる臓器(腎臓、心臓、脳など)への血流量が減少し、多臓器不全の状態になります。
人間の血液が菌に侵されて、「負ける(まける)」状態です。
腎盂腎炎になると、この敗血症性ショックを起こす可能性が出てきます。
ですから、腎盂腎炎と診断された場合、入院して点滴による抗生剤治療が必要になります。
膀胱炎も、腎盂腎炎に移行してしまうと一大事。
ショック状態になるかもしれないと考えれば、膀胱炎も“たかが”とは言えませんよね。
膀胱炎になると、生命保険に入れない?
ここまで、膀胱炎が腎盂腎炎になると非常に怖い敗血症性ショックを起こすことがある、とお伝えしてきました。
では、ここからは生命保険と結び付けて考えていきたいと思います。
膀胱炎は、全く起こさない人もいれば、1年に数回繰り返す・・・という人もいます。
たった一度で済んでしまえば、生命保険の新規加入ができない、引き受け基準緩和型でないと入れない、ということにはならないでしょう。
(「引き受け基準緩和型」というのは、特約を付けて条件付きで加入を認めてもらえる商品のことで、<生命保険と健康状態の関係「喘息」>でお伝えしています。)
しかし、膀胱炎を繰り返す人は、何度も繰り返します。
それは、上で述べた<膀胱炎の要因>が、生活習慣と密接な関係にあるからです。
販売員の20代の女性が、膀胱炎に“慣れっこ”になっていたこともありました。
さすがに、何度も繰り返し罹って治療を受けている場合は、膀胱炎を風邪と同じ扱いにはできないでしょう。
たった一度の膀胱炎ですら、腎盂腎炎→敗血症という経過をたどることもあり得ます。
回数が多ければ、それだけ可能性も高くなるのですから。
敗血症まで至らなくても、腎盂腎炎は入院治療が基本ですから、膀胱炎を繰り返す人はそれだけ入院の可能性が高くなります。
そうなると、生命保険会社は入院給付金を支払うリスクが発生します。
それだけではありません。
膀胱炎治療で抗生剤を繰り返し内服している人は、その薬に対する「耐性菌」ができてしまうことが多くなります。
耐性菌ができると、その薬が効かなくなってしまうのです。
製薬会社が苦労して新しい薬を作っても、どんどんそれに耐性ができてしまうという“いたちごっこ”の状態で、昨今非常に問題になっています。
抗生剤が効かなければ、腎盂腎炎や敗血症へ移行する可能性も高くなります。
ということは、たかが膀胱炎と安易に考えて繰り返すことは、身体にとってよくないこと。命に関わる状態にもなりうるのです。
たかが膀胱炎なら、生命保険加入時に告知する必要はないよね?
確かに、そうかもしれません。
風邪でクリニックに受診した程度のことを、加入時に伝えないですものね。
しかし、繰り返している場合には要注意です。
もし新規加入を検討している場合は、必ずその旨を告知しましょう。
黙っていると告知義務違反となり、契約解除となったり保険金が支払われない事態が発生するかもしれません。
もちろん、生命保険に加入していて腎盂腎炎で入院した場合には、保険金の請求をしましょう。
短期入院で終わるケースがほとんどですが、せっかく払い込んできた保険料ですから、もらえるものはきちんともらっておきましょう。(*^-^*)
いかがでしたか?
膀胱炎なんてたいしたことないし、口にするのも恥ずかしい・・・と思っていたあなた。
本当はとっても怖い病気でもあることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。