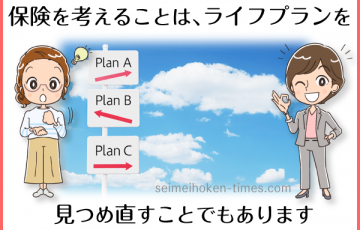誰にもやってくる「老後」って、いつから?
人生で大きな出費は、
1位:マイホーム
2位:生命保険
3位:教育費
と言われています。
2位が生命保険!?と思ったあなたは、こちら(生命保険が「人生で2番目に高い買い物」になるかどうかはあなた次第!?)の記事を読んでみてくださいね。
「人生で大きな出費」というと、1~3位は上のようになりますが、「あなたが心配なお金は?」と聞かれたらちょっと違うのではないでしょうか?
私ならここに、老後費用」が入ります。
でも、老後っていつからなのでしょうか?
政府は、「高齢者」の定義を75歳と検討しているようです。
(その前に、65歳を准高齢者とするなどの意見も出ているようですね。)
でも、私達がお金の面で老後を考えるときは、75歳ではないと思います。
60歳なり65歳なり、今と同じように働けなくなったときのことを考えるのではないでしょうか。
今回は、誰にでも訪れる老後に関する費用、それをめぐる生命保険についてお伝えしようと思います。
老後の費用は、いくら必要?
『老後の費用は、いくら用意したら安心ですか?』
この問いに、はっきり答えられる専門家はいません。
こども保険の記事(こども(学資)保険に関して理解しておきたい基本を解説!)でもお伝えしたように、人間はわからないことに不安になります。
子供の教育費は、その子の個性やどの学校に進学するか、大学だけでもどの学部・学科を選択するかで、必要なお金は変動します。
大学進学費用に数千万円用意しなくてはならないのか、それとも数百万円で済むのか・・・それは、正直その時にならなければわからないものです。
子供の学力やどの道を志望するのかにもよります。
数千万円単位のお金がからむのに、予定が立てられないのです。
老後費用も、これと同じことが言えます。
老後って、何年あるのでしょうか?
65歳から20年・30年、それとも35年・・・?
何歳まで生きるか、まずわかりません。
それに、定年退職の年齢も会社によって様々ですし、定年まで働き続けられるかどうかもわかりません。
10年分の生活費用と35年分では、3.5倍違います。
年を経ることで、健康上の問題も出てきます。
何の病気もなく老衰で亡くなる「ピンピンコロリ」とは、限られたごく一部の人だけなのです。
私のように、20代から持病を抱え、それに少しずつ違う病気がくっついて・・・となると、年をとったらどうなってしまうのか?という不安が常にあります。
また、どんなに健康な人でも、ある日突然脳梗塞を発症して寝たきりになることだってあります。
糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病なら、自分自身の心がけでなんとかなるものもあります。
しかし、多くの病気は自分の努力だけでは予防することができないのです。
教育費も老後費用も、先がわからないからこそ、不安になるのです。
では、老後費用はどのくらいが「相場」なのでしょうか?
少し調べただけでも、3000万とか1億とか、なんでこんなに幅が広いの!?というデータが出てきました。
でも、この金額を信用してよいのでしょうか?
相場へ合わせることに、意味があるのでしょうか?
自分以外の人が必要と思っている金額の統計データであって、あなたの望む生活費ではないのですから。
私の勤務する病院には、90代でも1人暮らしをしていて、自分で定期通院に通ってくるおばあさんがいます。
一方で、40代でも脳梗塞や脳出血で寝たきりという人もいます。
生活スタイル・価値観・健康状態、不確実なものばかりです。
老後費用がいくら必要なのか、いくらあったら安心なのか考えるのは、無理なことかもしれませんね。
老後費用は、国に任せておけばいい?
では、老後費用になんの備えもいらないのか?
そうではありません。
スウェーデンのような高福祉国の国とは違い、日本では将来を国に任せておけば安全、とは言えません。
年金をめぐるニュースでは、給付開始年齢の引き上げと給付金額の引き下げばかり話題になっています。
少子高齢社会のこの先、年金がいくらもらえるかなんて、わからないのです。
年金がなくなることはないでしょうけれど、「年金=標準的な生活を送る費用」とは限りません。
つまり、年金だけでは足りないという老後が待っている。
安心した老後に備えるためには、どうやって、いくら貯めたらいいのでしょうか?
老後の生活の柱となる年金について、少し考えてみましょう。
年金には、国民年金を納めていたら全員がもらえるはずの老齢基礎年金と、「2階建て」と言われる上乗せ分の厚生年金・共済年金があります。
どの年金をもらえるかは、現役時代の職業によって別れます。
自営業:国民年金のみ
会社員:国民年金+厚生年金
公務員:国民年金+共済年金
ただし、これでは足りないなと思ったら自営業の人は国民年金に上乗せで国民年金基金として積み立てることができます。
誰でも同じ金額がもらえるはずの老齢年金を基本に、老後費用を考えればいいですよね。
では、受給額はいくらでしょうか?
平成28年度は、78万100円です。
年額ですよ。
つまり、月6万5000円です。
やっていけますか?
これが、国が保障している年金額です。
それでいて、この金額すら引き下げようとしています。
高齢者を支える現役世代が少ないのですから、仕方のないことだとは思います。
でも、これでは暮らしていけない。
だからこそ、皆不安になるのです。
これに対し、厚生年金は平均給与30万円の人が40年加入した場合、年83万1000円、月69000円ほどの受け取り額になります。
(厚生年金は計算が複雑なので、概算です。)
厚生年金や共済年金は、現役時代に労使折半で積み立てています。
半分会社で積み立ててくれて、それを老後に受け取れるのですからお得ですね。
実際、これらの二階部分の年金は受け取れない人が多いにも関わらず、老齢基礎年金の金額よりも高いですね。
二つあわせたら、そこそこ暮らせるかも・・・という金額です。
また、これらの上乗せ部分の年金額は、現役時代の給与によって違います。
ここが老齢基礎年金とは違うところで、一律いくらと金額を出すことはできません。
働き方が多様化している現代では、今後どのような働きをするかはわかりませんから、厚生年金の金額は予想できません。
結局、老齢基礎年金の65000円だけでは、老後資金は足りないと言わざるをえません。
若かったら、がむしゃらに働いて稼げばいい。
でも、高齢になったらそうはいきません。
働けないのに、お金だけ出て行く・・・そんなことになるかもしれないのです。
老後を安心して暮らすためには、国にだけ頼っていてはいけない。
でも、現役時代にはマイホームに教育費でカツカツ(>_<)
そこで、老後の「もしも」に備えるための生命保険が誕生したのです。
老後費用を支える生命保険
老後を、年金だけで暮らしていけなかったら・・・?
その不安に応えるべく生まれたものが、個人年金保険です。
個人年金保険は、生命保険の基本である死亡保険とは違い、将来自分が受け取る目的で加入する保険です。(中には、死亡後には家族が受け取れる個人年金保険もあります。)
給与収入のある現役時代のうちに保険料の払込を終えておいて、それを年金原資とします。
生命保険会社はその預かったお金を運用して増やします。
そして、自分が高齢になったときに年金として分割して受け取ることで、公的年金にプラスしたお金が生活費として入るようになります。
給与収入がなくなると、毎月定額で入るお金が重要になります。
1年後に300万円もらえるとわかっていても、今をしのぐお金がなければ生活できません。
ですから、毎月もらえるお金が安心感につながるのです。
個人年金には、まとめて受け取る一時金形式を選べるものもありますが、生活費にするのですから、年金形式を選択するのが基本。
ただし、この受け取り方法によって、契約の種類が変わります。
<個人年金の受け取り方法>
終身年金 :一生受け取れるが、亡くなった後は受け取れない
確定年金 :生存・死亡問わず、一定期間は受け取れる
有期年金 :一定期間は受け取れるが、亡くなった後は受け取れない。
自分の老後が何歳までなのか・・・これが、老後費用を考えるネックです。
ですから、個人年金も老後の年齢をどう考えるかによって、受け取り方法を選択することになります。
長生きする人にとっては終身年金がお得ですが、自分がどうなるかはわかりません。
それに、せっかく払った保険料ですから、早死にして損をするなら家族が受け取れるものの方がいいかもしれませんね。
遺された配偶者の生活を保障できる商品にしたいと思えば、夫婦で入る「夫婦年金」もあります。
これは、考え方によります。
一番安心な終身年金は、一番保険料が高めになります。
一方で、有期年金なら現役時代に払い込む保険料を節約することができます。
個人年金は、老齢基礎年金だけでは不安という人、現金を積み立てるのは自信がない人には、老後の安心を支えてくれる保険商品と言えるでしょう。
個人年金に入ると、税金を控除してもらうことができます。
会社員なら、12月に年末調整を会社がやってくれますよね。
その時に、保険料控除証明書を持って行くと思います。
保険料を払い込んだ分だけ、所得から引いてくれるので。
国として老後を支えきれないから、その分自分で積み立ててくれる人にはちょっと税金おまけしますよ、というものです。
となると、個人年金は国が応援するだけの価値がある、と考えることもできますね。
個人年金は本当にお得?安心?リスクもしっかり考えよう
では、将来国にまかせておけないのなら、個人年金で備えておかなければならないのでしょうか?
入る余裕のある家庭なら、入っていて間違いではありません。
しかし、毎月住宅ローンに教育費を支払い、カツカツの生活をしている現役世代は難しいでしょう。
昨今は晩婚化によって出産年齢も上がっていますから、子供が成人になる前にお父さんが定年退職を迎えてしまうという家庭も多くあります。
そんな家庭では、現役時代に住宅ローンに教育費、同時に老後費用まで貯めておかなければなりません。
毎月の生活がカツカツでお小遣いも減らしているのに、これ以上生命保険料を上げるわけにはいかない、というのが実状ではないでしょうか。
20代・30代の若いうちから加入すれば、時間が味方をしてくれます。
積み立て期間が長い分、毎月の保険料を安くすることができます。
しかし、40代、ましてや50代で新たに加入するのは、少し苦しいかもしれません。
年齢が上がるほど積立期間が短いので、その分保険料が高くなるからです。
(保険料を安くすると、将来の年金額となる原資が少なくなります。)
また、子供の大学進学資金でお金が必要になって、どうしても解約せざるをえなくなったら??
多くの個人年金保険が、25年以上経過しなければ解約返礼率が100%を超えません。
元本割れ、ということですね。
もしこれを現金として貯めておけば、もしもの時に使える現金として残しておくことができます。
しかし、生命保険にしてしまうと、お金が必要になった時点で解約すると、損を確定してしまうことになるのです。
こども保険の記事でも提案しましたが、教育費の積立が子ども保険でなくてはできないかといったら、そうではありません。
他にも、死亡保険や投資信託を活用することもできます。
同様に、老後の費用に備えるのも、個人年金だけではありません。
老後資金なら、死亡保険や投資信託に加えて、最近話題になっている確定拠出年金も選択肢にあげることができるでしょう。
もちろん、現金としてコツコツ積み立てておくというのもアリ。
ある意味、何にでも使える現金が一番の保険かもしれません。
生命保険会社は慈善事業ではありませんから、人件費や広告費などの経費も含まれた金額が、私達の支払う保険料です。
保険会社の運用によって多少は元本を増やしているでしょうけれど、金利の低い現代では微々たるもの。
その証拠に、加入して数年は、解約返戻金が払い込んだ保険料の半分にもならない生命保険が、なんと多いことでしょうか。
これは、それだけ生命保険には経費がかかり、保険料のうち保険会社側の取り分が多いということの現れです。
冒頭に挙げた人生の出費第3位までで、私達は数千万円を支払います。
もしもの備えをどれだけ生命保険で対応するかは、自分のライフスタイルや家族構成、それから貯蓄体質があるかどうかなどを踏まえて考える必要があります。
答えのない問題だけに、難しいですねぇ。
まずは
- 自分が老後に受け取れるもの(年金)は何か
- 老後には毎月いくらくらいのお金があれば生活できるのか
- そのときまでにどれくらいの現金を残しておけるのか
これらを、ざっとイメージすることから始めてみてはいかがでしょうか。
それに、今の生活を見直して無駄な出費を削れば、個人年金の保険料なり老後資金の積み立て費用を捻出できるかもしれませんね(*^-^*)