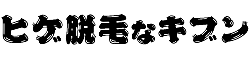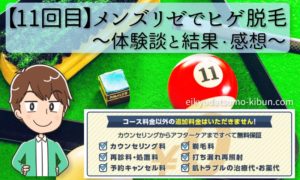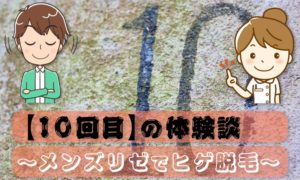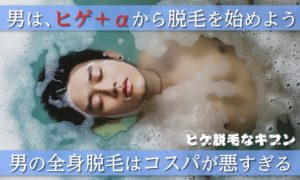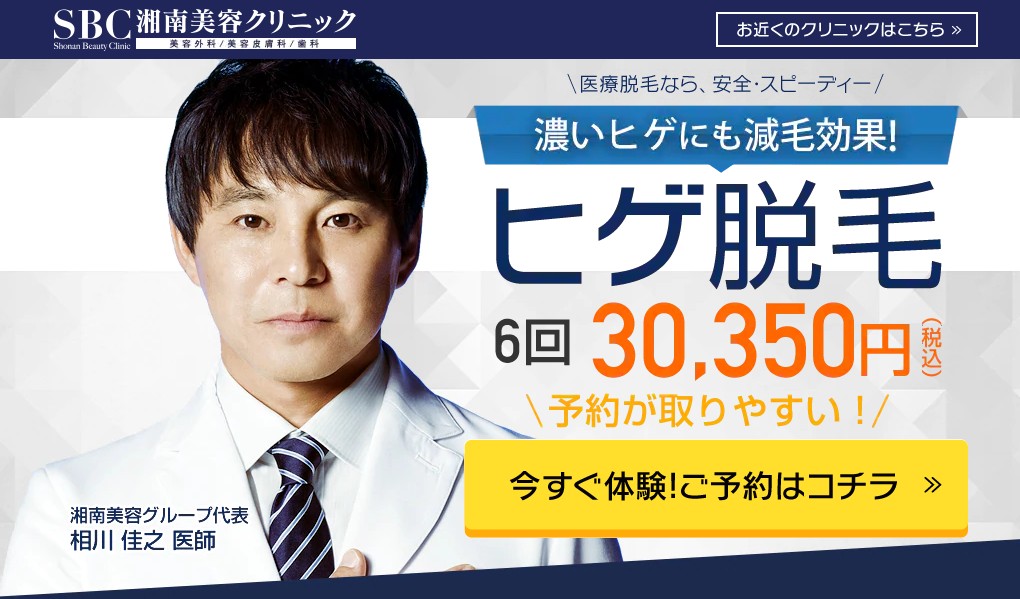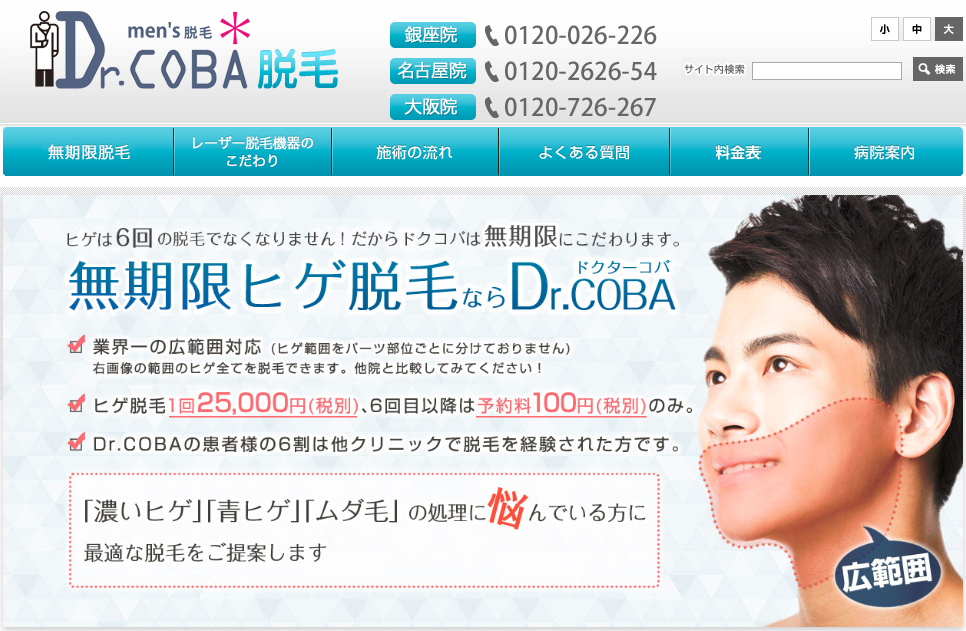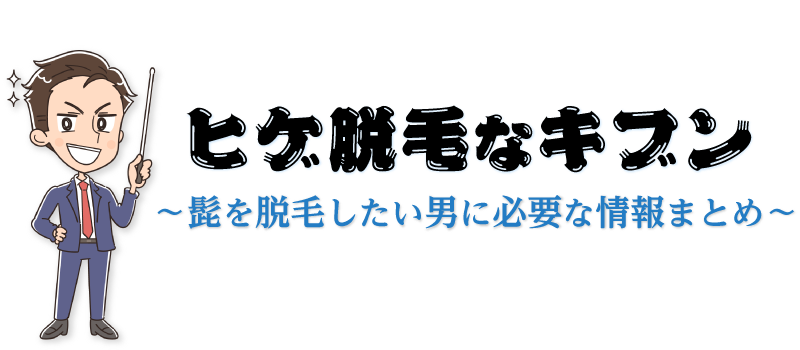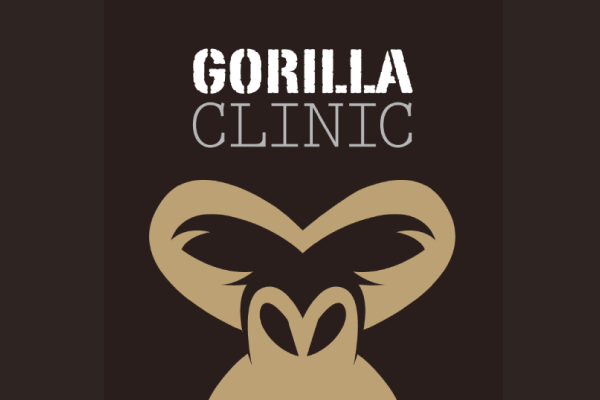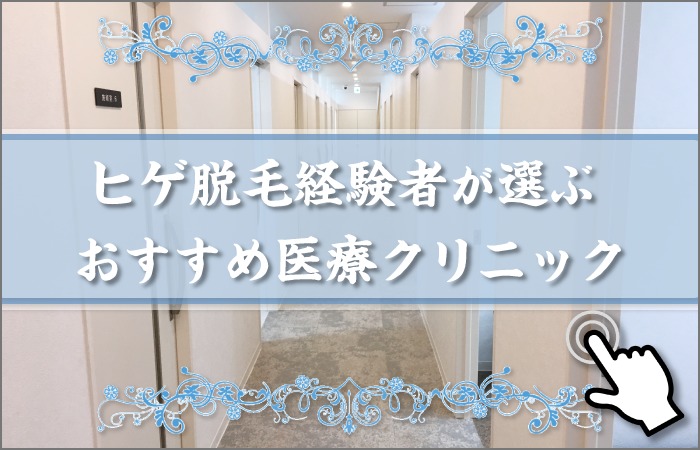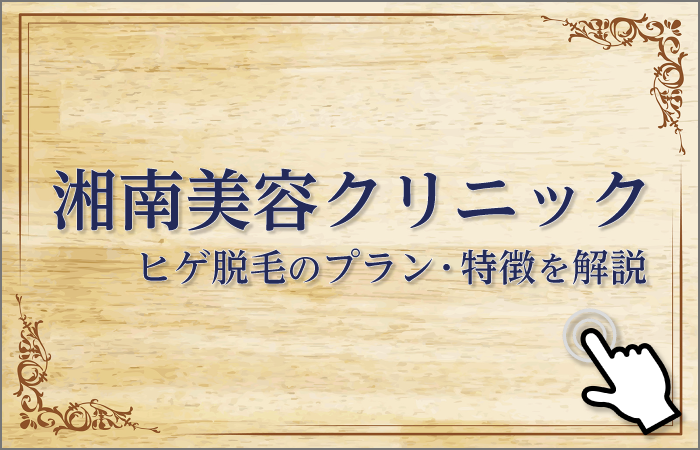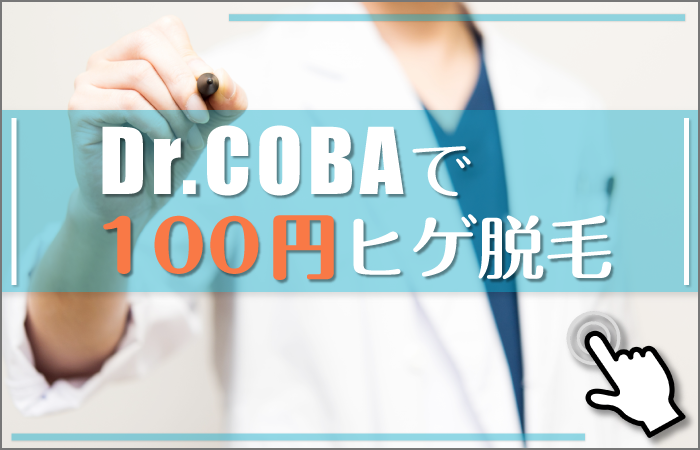この記事の目次
髭の変遷:今も昔もあまり変わらない…?
現代日本では、男なら誰しも当たり前に生えてくる髭をなぜ忌避する傾向にあるのだろうか。
なぜ髭を剃るのが、“当たり前”のマナーとなっているのだろうか。
それは、髭の歴史を紐解いてみれば分かるかもしれない。
男に髭が生えなかった時代はない。
相応の「対策」が時代ごとにあったはずだ。
時代ごとの髭
原始~戦国時代

そもそもの髭は、過酷な環境で生き残るために欠かせないもの。
寒さを凌ぐためであったり、身を守るためであったり、狩りをして生きていかなければならない時代には、男の髭は生命維持のために重要な役割を持つものであった。
時代が進むと、権威や神聖さをアピールするものとしても重宝され始めた。
奈良時代には、聖徳太子が髭を生やし、
平安時代には、藤原道長が髭を生やし、
鎌倉時代には、源頼朝が髭を生やし、
室町~戦国時代には、多数の武将が髭を生やした。
これらは、威厳の誇示のためや「男」を象徴させるために用いられたようだ。
髭は男になくてはならない存在であったことが窺い知れる。
江戸時代
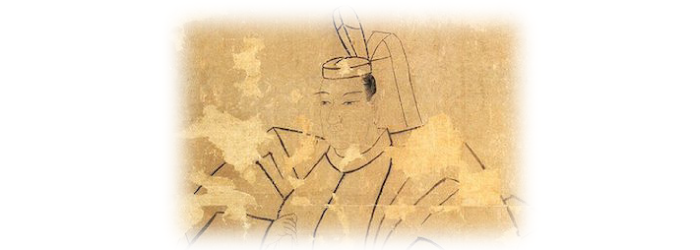
ところが、江戸時代を迎えると、「男=髭」の風潮は薄まっていく。
江戸幕府を開いた徳川家康から三代目の家光までは髭を生やしているが、四代目の家綱は髭を生やしていない。それどころか、十一代目の家斉を除いて、十五代目の慶喜まで誰も髭を生やしていないのだ。
家綱が武力重視の武断政治から学問(儒教)を重視する文治政治に切り替えたことが大きいのだろう。
特に大きな転機となったのは、家綱が「大髭禁止令」なる法令を出してしまったことか。
太平の世では、力を誇示して生きる武士の存在が不要になったうえに、髭をぼさぼさに生やした反体制的な武士崩れの「かぶき者」を排除するため、髭を生やした者を取り締まり、罰金を科したのだそうだ。
これ以後は庶民でも髭を生やすことはなくなり、ツルツルが基本となったようだ。この時、明確に、髭はアウトなモノ(アウトロー:無頼なモノ)と認識され始めたに違いない。
男は髭で自分を誇示できなくなったのだ。
明治時代

明治時代になると、江戸時代とは打って変わり、「髭=文明」の象徴とされるようになる。
外国人の到来が、日本に新しい風を吹き込んだのだ。
伊藤博文、大久保利通、陸奥宗光、板垣退助など多くの政治家や権力者がこぞって髭を生やしている。それも、今では考えられないような。
明治時代に髭が流行っていたのは確実だろう。昭和時代

昭和時代に入ると、また髭の流行は下火になった。
髭を剃った男性の方がモテるという認識が一般化し始めたからである。
その原因は、安全カミソリの普及だ。
髭を剃るという行為が大衆に求められるようになったのはこれからなのは確か。
一方、戦時中は多くの軍人が髭を生やしていた。
やはり髭は権力をアピールするにはうってつけのアイテムだったようだ。
ただ、一般兵士は安全カミソリを使っていたそう。
終戦後は、髭を剃るのが当たり前になる。
特に高度経済成長期のサラリーマンにはみな、ツルツルが当然のものとして定着し出す。
「朝の髭剃りはエチケット」とまですでに言われていたようだ。
平成時代

そして、平成時代。
ご存知の通り、サラリーマンは髭を剃るのが義務である。
さらには、髭は不衛生・不潔の象徴とされてさえ久しい。
しかし、おしゃれヒゲなど職業によっては、髭を受け入れられている部分も少なくない。
むしろ、髭によって自分の個性(アイデンティティ)をアピールする目的で用いられ始めてもいる。
ただ、自由に髭を生やせる環境を見つけるのは、非常に難しいのが現状である。
(参考:男とヒゲの歴史-貝印株式会社)
髭対策の歴史

髭の流行り廃りは時代によって移り変わっていったことが分かる。
髭を生やしてよい時代はともかく、江戸時代など髭を生やせない時代の庶民は、どのようにして髭を処理していたのだろうか。
今以上の苦労があったのか、それとも、ある程度剃れておけばよかったのだろうか。
どちらにせよ、髭剃りが面倒なものであったことに違いはないだろう。
髭剃り(体毛処理)の試行錯誤
世界的な流れを見ると以下のような処理方法であった。
- 遡ること10万年以上前、ネアンデルタール人は二枚貝で髭を挟んで抜いていた。
また、鋭く尖らせた石器で体毛を剃っていたようだ。
- 古代エジプトでは、体毛は不潔の象徴であり、金や銅でできた剃刀で体中の毛を剃っていた。ファラオ(王様)は全身をツルツルにして、カツラを被っていたほど。
- 古代バビロニアでは、5000年前程から、灰汁と油を混ぜたものをシェービングクリーム代わりに使っていた。
- 古代ローマでは、2200年ほど前、奴隷もしくは敵と区別するために、ローマ人の上流階級の人々が髭剃りを始め、それが自由市民にまで広まった。
これにより全世界に髭剃りが広まったのである。
- ローマ帝国崩壊後から中世までは、理容師が髭剃りを行う。なお、この理容師は外科医、歯医者としての役割も持ち、髭剃りや散髪は専門家が行う仕事であった。
この頃から、「髭を管理」する文化も根付いていく。
- 1900年になると、使い捨て替え刃のT字型安全剃刀が発明される。これで、髭剃りが一般的なものとして普及し始めた。
- 日本では…
日本では、室町後期~江戸時代にかけて、月代(さかやき)といういわゆる「ちょんまげ」が男性の一般的な髪型であった。それには、一銭ほどで髪結いをしてくれる「一銭剃」と呼ばれる床屋が起源となったとされる。
髭を剃らなくてはならない江戸時代の庶民にはさぞ、重宝されたことだろう。
また、江戸時代には「日本剃刀」という剃刀があり、鍛冶屋が作っていた。
髭剃りはすでに商売となっていたようだ。
これまでの髭とこれからの髭

10万年以上前から、男は髭と戦い続けてきたのだ。
社会情勢によって髭が流行したり髭を禁止されたりと、いつも男は髭で苦労してきたのだな、とため息を吐きたくなる。
歴史が、今この現代日本人の髭剃りの苦労や苦悩を証明してしまっている。髭剃りの面倒さを連綿と受け継ぎ続けてきたのだ。
男は髭に悩まされる宿命なのか…。
毎朝の儀式のようなものなのか、やはり髭剃りというものは。
日本だけでなく、全世界の男たちが髭剃りの面倒さに憂鬱になっているのだろう。
歴史には抗えないのか…?
これからも男は髭剃りに苦心し続けるのだろうか。
髭の価値とは
過去の歴史を見てみても、髭の有無を決めるのは常に権力者であった。庶民はそれに従う以外の道がなかっただけに過ぎない。
恣意的な判断で、男なら誰しも生える髭を制限されてきたのである。
今日、髭の制限は多少ゆるくなったほうだろう。
しかしそれでも、今なお髭剃りという重労働を強いられていることに変わりはない。
長年、根付いたこの状況を打破できる方法は皆無に近い。
人々の深層心理の奥深くまで、「髭」というものの存在価値・存在意義は決まり決まっている。
髭を生やせば権力者足り得るか。いや、それはあり得ない。
良くも悪くも現代人は自由であるが、なぜか髭だけはタブーな存在とされている。
髭はその価値を失くしたとさえ言えるだろう。
なんせ使い道がない…。
そう、もうすでに髭は不要なものなのだ。
ヒゲ脱毛が新たな未来を作る
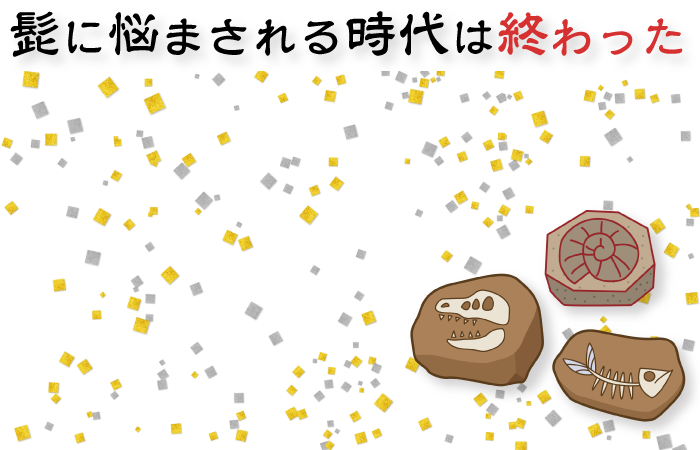
個人の裁量でどうにもならない事を忌避され制限されてきたのが、「これまでの髭」だ。
科学の進歩した今こそ、髭に悩む必要のない人生をスタンダードにするべきだろう。
髭はもはや時代遅れの遺物なのである。
悪しき歴史や慣習を変えることができないのなら、「ヒゲ脱毛」を徹底させることで、髭の制限や髭剃りに一切悩まされない人生を作り上げよう。
10万年以上に渡る長き男の髭のとの戦い。
それが決着するとき、人類全体が新たな未来に向かって進歩できるはずだ。
髭のない男および髭剃りに苦労しないのが当たり前の毎日。
ヒゲ脱毛なら、それが実現可能だ。
「これからの髭」は、もうない。
髭はもう死んだのだ。