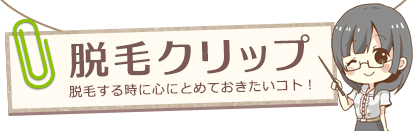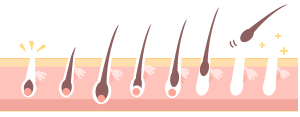医療レーザー脱毛に保険が適用されない理由
脱毛をするには、エステサロンに行くか、クリニックに行くか、どちらかを選ぶことになります。
「病院で脱毛すれば、保険証が使えるから安くなるんじゃない?」
と、クリニックを選ぼうと思っている人もいるのでは?
しかし、病院に行っても脱毛料金が安くなることはありません。脱毛の施術では、健康保険は適用されないからです。
脱毛は「自由診療」です
病院の診療内容には、保険診療と自由診療の2種類があります。
わたしたちが普段病院に行くときは、保険診療を受けていることが多いのではないでしょうか。風邪をひいたから病院でみてもらった、肌荒れしたから皮膚科を受診した、生理不順で婦人科を受診した。などなど。
こういった「具合が悪いから病院に行く」といった場合、基本は保険診療になります。
保険診療とは、健康保険から医療費の負担をしてもらえるため、自己負担が少なくて済むものです。実際には1万円かかった治療を受けたとしても、「3割負担」で3千円しか払わなくていいんですね。残りの7千円は健康保険から支払われています。
ただ、いくら3割負担だと言っても、実際にはわたしたちはもっと負担をしています。それが、毎月の保険料です。会社員の方なら給料から、健康保険料が引かれていますよね。国民健康保険の方なら、毎月引き落としか振込用紙による払込で支払っていることでしょう。
こうしてわたしたちが支払った保険料を原資に、治療を受けた際の医療費を軽減することになっています。これが、健康保険の仕組みです。大きな病気をして医療費が何百万円もかかったとしても、みんなが支払っている保険料からかなりの金額が負担されているので、自分で負担する金額は少ないです。
さて、脱毛で健康保険が使えないのはどうしてでしょうか?
美容整形を例に考えてみると分かりやすいと思います。
「鼻を高くしたい」とか「脂肪吸引したい」といった美容整形は、病気ではありませんよね。
もし、美容整形に保険が使えるとしたらどうでしょう? みんなが毎月支払っている大切な保険料を、病気でもない人のために使ってもいいのでしょうか。もっと、救うべき人がいるのではないでしょうか。病気でもないものにまで保険を適用しているとキリがありません。
そこで、保険が適用できるのは、基本的に病気やケガなどをしている人に対する治療のみ、ということになっています。
※病気などの治療でも、未承認薬を使う場合など、保険が適用できない治療もあります。
美容整形や脱毛に関しては、保険の適用はありません。また、歯の治療には保険が使えますが、歯列矯正やホワイトニングといった「審美歯科」についても保険の適用ができません。
自由診療とはどういうもの?
医療レーザー脱毛の場合は、たとえ病院に行ったとしても保険は適用されません。保険が使えない診療内容のことを、「自由診療」と言います。
自由診療というのは、ただ保険が使えないということだけではありません。特徴的なのが、「クリニックごとに自由に料金を決められる」ということです。
保険診療の場合、「検査○点」、「注射○点」というように点数が決まっていますよね。点数をもとに、治療費が決まります。
自由診療の場合は病院ごとに自由に料金を設定できるという特徴があるのです。つまり、まぶたを二重にする手術を受けたとしても、A病院では10万円、B病院では20万円、というようにかなり料金に差が出てしまいます。
要は、自由診療というのはエステサロンと同じように、料金を高くするのも安くするのも自由だということ。クリニックごとに、儲けも考えつつ、かと言ってお客さんが払える程度の金額……というのを模索しながら、脱毛料金を設定しています。
このように、クリニックでの医療レーザー脱毛は、保険の適用はありません。病院ならどんな診療内容でも保険が使えるわけではないのです。保険が適用できないので料金が安くなるわけではありませんし、わたしたちが支払う金額というのはクリニックのメニュー表に載っている金額そのままです。
医療レーザー脱毛はあくまでも美容目的の診療ですので、自費で通うことになるということを理解しておいてくださいね。なお、料金のことで分からないことがあれば、カウンセリングに行ったときにでもしっかり質問しておきましょう。